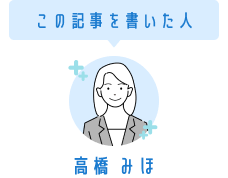UIデザイン改善【基礎編】~システムデザイン改善を検討する“デザイナーでない”リーダー層へ~
近年、システムのデザインがプロジェクトの成否に及ぼす影響が注目されています。理由は、デザインが単なる見た目の美しさを超え、ユーザー体験や効率性、さらにはビジネス成果に直結する重要な要素であることが認識されてきたからです。
しかし、システム開発や改善を進める中で「デザイン」は後回しにされがちです。この記事では、プロジェクトのリーダーや中心的役割を担いデザイン改善を検討する皆さんに役立つ知識や具体例をご紹介します。
この記事の目次
1.システムの使いにくさを引き起こすNGデザイン
デザインの課題は、往々にして感覚的な違和感として表面化します。しかし、それを共通認識として具体化しない限り、問題解決に向けた建設的な議論は難しいものです。ユーザーにとっての「使いにくさ」は、デザイナーや開発者が意図しない形で発生することが多く、その根本的な原因を言葉にしたり可視化して共有することが重要です。本章では、よく見られるNGデザインの例を挙げ、共通認識を深めることで、具体的な課題解決につながる考察を提供します。
NG1|乱雑なデザイン
秩序がなく整理されていないデザインは、ユーザーを混乱させます。見た目が整理整頓できていない場合、情報がごちゃごちゃして見えるため、利用者は「何をすれば良いのか」を瞬時に把握できず、作業効率が著しく低下したり結果的にシステムから離れてしまう可能性があります。
課題例
- 情報のまとまりがない画面や見づらいメニュー構成。
- キャンペーンバナーや商品カテゴリーがランダムに配置され、視線の動きが定まらない。
解決策
- 情報のグループ化:視覚的なヒエラルキーを活用することで、一目で内容が理解できる構造を設計します。たとえば、商品カテゴリごとにカラーコードを使って一貫性を持たせます。
- 視覚的ヒエラルキーの活用:タイトルを大きくし、サブ情報を小さくするなど、重要度に応じた優先順位を明確化します。
- プロトタイプでのテスト:ユーザーに複数のレイアウトを見せ、クリックヒートマップを活用して改善点を発見する。
NG2|瞬時に理解できないデザイン
情報が過剰に詰め込まれたり、ユーザー視点に立ったデザインになっていない場合、混乱を生む原因となります。情報量が多すぎることで、重要なポイントが埋もれてしまい、何を優先すべきか判断できなくなり操作性を大きく低下させることもあります。
課題例
- 情報量過多で重要なポイントが埋もれてしまう。
- 初心者向けのシステムで、各操作手順が説明不足。
解決策
- 最小限の情報に絞る:画面に表示する情報は最重要なものに限定し、その他の情報はドロップダウンメニューや詳細画面に収める。
- 視覚的に理解しやすい工夫:適切なアイコンやチャートを活用し、ユーザーが一目で内容を理解できるようにする。
- オンボーディングプロセスの設計:初回利用時に簡易的な操作ガイドやツアーを提供。
NG3|非直感的な操作導線やボタン
ボタンや導線が直感的でない場合、ユーザーは行動を阻害され、操作ミスを引き起こす可能性が高まります。例えば、一般的には「キャンセル」ボタンは赤色で表示されることが多いですが、それが異なる色や形状で表示されると、ユーザーは誤解して操作を躊躇することがあるなど無意識に過去の経験や常識を基に操作するなど考慮が必要です。
課題例
- ユーザーの意図を汲まないボタン配置やカラー設計。
- 入力完了後の「次へ進む」ボタンが見づらい位置に配置されている。
解決策
- 業界標準の採用:色や配置を他のシステムと統一しユーザーの期待を裏切らない設計を行う。
- ユーザーテストを実施:ボタンの配置や色の選択肢をテストし、意図と異なる動作が発生しないかを検証。
- 視覚的なフィードバックを提供:ボタンを押した際に明確な視覚フィードバック(色の変化やアニメーション)を実装する。
このように、NGデザインの特徴を言語化して共通認識を持つことが、課題解決への第一歩となります。これにより、当事者間での的確な議論が可能になり、より効果的な改善に繋がるのです。次章では、こうした課題を具体的に解消するデザインアプローチについて掘り下げていきます。
2.システムの使いにくさをデザイン面からアプローチ
デザイン改善は単なる見た目の調整ではなく、使いやすさや効率性を向上させることで、ビジネス目標達成を支援する重要な取り組みです。特に、システムが使いにくい場合、その改善をデザイン面から行うことは、ユーザーの満足度を大幅に向上させる可能性があります。以下では、具体的なアプローチを示し、読者であるマネージャー陣やリーダー層の皆様がデザイン改善を効果的に進められるようサポートします。
1:一瞬で何ができるシステムか分かるシンプルなデザイン
シンプルなデザインは、ユーザーがシステムの機能を直感的に理解できるため、使い勝手を大幅に向上させます。複雑すぎるデザインではなく、必要最低限の要素を配置することで、ユーザーが迷わず操作を進められる環境を提供します。
成功ポイント:一貫性のあるレイアウトを採用し、視覚的な混乱を排除。アイコンやラベルを工夫し、直感的な操作を可能に。
2:無意識な行動原理を応用、人間工学に基づくUIデザイン
人間の無意識な行動原理を応用することで、使いやすいインターフェースを構築できます。例えば、人間工学に基づき、ボタン配置や操作導線を設計すると、ユーザーは自然と正しいアクションを取ることができます。
成功ポイント:ユーザーの目の動きや手の動きに基づくデザイン。操作の流れをスムーズにする「F字型レイアウト」などを採用。
3:興味関心が薄いユーザーにも使いやすいデザイン
システムに興味関心が薄いユーザーを考慮することは、ターゲット層を広げるために重要です。デザインが直感的でわかりやすいほど、関心の薄いユーザーにも受け入れられやすくなります。
成功ポイント:初心者向けの簡易モードを追加。説明動画やガイドを活用し、操作をサポート。
3.時にはトライアンドエラーで!UIデザインと相性抜群、ABテスト!
デザイン改善の効果を検証するためには、ABテストが有効です。これにより、どのデザインがよりユーザーに受け入れられるかを数値的に分析できます。ABテストとは: 異なるデザイン案を比較して、効果を測定する手法です。例えば、ボタンの色や配置を変えることで、クリック率やコンバージョン率がどのように変化するかを検証できます。
実施ポイント:目的やターゲット層を明確に設定。データを収集し、意思決定の参考資料を作成。詳細はこちらの記事をご覧ください。
4.デザインでの改善がほぼ決まったらやること
デザイン改善の方向性が固まったら、次に進むべきステップとして人材や工数の検討が必要です。
理想のデザイナー像: デザイン改善を成功させるには、創造性と実行力を兼ね備えたデザイナーが不可欠です。そのスキルセットを明確にし、適切な人材を採用する必要があります。
内製か外注か: デザイン工数を確保する際には、内製と外注のどちらがより適しているかを慎重に比較しましょう。例えば、内製は企業文化との調和が期待できますが、外注は専門知識を最大限活用できます。詳細はこちらの記事をご覧ください。
5.リーダーが実施すること・デザイナーに任せること 6選
盲目的にデザインの力に頼っていませんか?
デザイン改善の検討段階にいるマネージャー・リーダー層に向けて、システムの使いにくさを引き起こすNGデザイン例とその解決策を提示しました。
デザインの力は絶大ですが、万能ではありません。デザイン改善が本当に課題解決の最適な手段であるかを慎重に判断することが求められます。
▼“デザイナーでない”リーダー層で実施すること
1.現在の課題がデザイン改善で解決可能かを分析する
問題の本質を明確にし、デザイン改善が最適な手段であるかを見極めます。
2.課題に対する適切な手段を検討し、デザイナーと相談して最終決定
必要なリソースや手法を明らかにし、デザイナーとコミュニケーションを図ります。
3.工数の合意
デザイナーや関係者とスケジュールやタスクの範囲について調整を行います。
4.工数に伴う予算の確保
必要な予算を見積もり、経営層に提案するなどのプロセスを担当します。
5.プロジェクトの方向性を定義
ビジネス目標やユーザーターゲットを明確にし、デザイン改善のゴールを設定します。
6.デザイン改善の成果指標を設定
改善の成否を図るためのKPIや指標を設けます。
▼デザイナーに任せること
1.専門的なデザインの良し悪しの判断
見た目だけでなく、UI/UX観点での専門的な判断を行います。
2.具体的なデザインコンセプトの提案・実装
システムやビジネス要件に合ったデザインを具現化します。
3.ユーザー調査に基づくデザイン改善
ユーザー調査の結果を踏まえ、デザインに反映させる。
4.プロトタイピングとユーザーテストの実施
モックアップの作成や実際のユーザーによるテストを通じて、デザインを検証します。
5.業界標準や最新トレンドに基づくUIガイドラインの構築
プロジェクト全体で一貫性のあるデザインを実現するための基盤を作成します。
6.デザインに必要なツールの選定と活用
例えば、FigmaやAdobe XDなどを活用し、効率的な作業を実施します。
デザインを着手するにあたり重要な点は、「そのデザインで何を成し遂げようとしているか」ということです。作成して欲しいデザインの方向性や色味、期日などを伝えたらプロだから丸投げで良いということは決してありません。
そのデザインがどういった際に使われ、これまでにどんな課題があったから改善が必要で、方向性としてはこんなイメージはあるものの、どの部分には検討の余地があるなど、しっかりと定義をすり合わせる工程は必須になります。
とはいえ、直ぐに対応が必要だ!社内に空いているデザイナーがいない。グラフィックはできるがUIデザインは自信がないなど、 記事を読んでさらに具体的なアドバイスが必要な場合は、「UIナビ」または「デザインレスキュー」サービスをご活用ください。専門的な視点から課題解決をお手伝いします。
「UIナビ」では無料のUI診断を受け、改善ポイントをプロのデザイナーよりフィードバックをもらえるためお勧めです。「デザインレスキュー」は、継続的にデザイナーの工数を確保し作業を外注したい方にぴったりです!お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください!
この情報は役に立ちましたか?
カテゴリー: