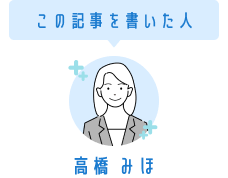UIデザイン改善【入門編】~予算ゼロでも始められる!取り組み施策ガイド付き~
この記事の目次
1.デザインは費用対効果が図れない?
ビジネスでは、費用をかけた施策がどのような効果を生むのかを見極めることが重要です。特にデザイン改善に興味を持ちながらも予算確保に苦戦している方にとって、その価値をどう伝え、効果をどう測るかは頭を悩ませるポイントではないでしょうか。
デザイン制作のコストは、人件費やシステム利用料など具体的な数値で評価しやすい部分があります。しかし、「デザインの改善」による費用対効果は目に見えづらく、社内での承認を得る際にハードルを感じるかもしれません。
ですが、消費者にとって魅力的なUIは、ユーザー体験を向上させるだけでなく、離脱率の低下や購買意欲の向上など直接的な成果にもつながることをお伝えしたいと思います。この記事では、デザイン改善の効果を説得力を持って伝えるための視点や考え方を、わかりやすく解説します。
デザインの優先順位は?UIデザイン改善の第一歩は「判断」
少し脱線し仕事の優先順位について触れていきます。
仕事の優先順位は、「ToDoリスト」だけでなく、「緊急度」と「重要度」に基づいて決めることが効率的と言われています。この際、時間管理のフレームワーク「時間管理マトリクス」が役立ちます。短期的には、緊急かつ重要な項目(A)から取り組むのが基本ですが、緊急ではないが重要なタスク(CやD)には、計画的な対応が必要です。
費用対効果が図れない=緊急度が低い?
それでは、「デザイン改善」に話を戻しましょう。デザイン制作や改善は費用対効果が計りづらいため、優先順位が低くされがちです。しかし、ここで着手するための費用や可能性・リスクなどの分析に時間をかけるよりも、「まずやってみる」ことが重要です。小さな変化を実施し、その実際に発生した差分を分析・検証することを繰り返していくことです。それでも一歩踏み出すのが難しい場合には、例として「月に1~2回デザイン改善に取り組む」や「ABテストツールの無料お試しを使用してみる」など具体的な行動を伴う努力目標を設定し、PDCAサイクルを回してみると、そこから新たに見えてくることがあると思います。
デザイン改善の効果は、全てに効果的な絶対の答えはありません。ですが、効果を測れないわけではなく、適切な目標設定と効果測定で評価可能です。たとえば、ホームページやLPのUIデザインを改善すれば、コンバージョン率の向上や離脱率の低下などの良い結果が見込めます。また、顧客満足度を高め、問い合わせ対応の負担軽減などの間接的な効果も得られるでしょう。
費用対効果の明確化が必要なら、顧客満足度調査でデザイン評価を収集し、課題を整理して改善に着手するのが堅実です。デザイン改善は、小さな一歩でも、大きな成果につながる可能性を秘めています。
2.デザインへの理解は目的達成へ寄与するのか
そもそもデザインとは
デザインという表現は様々な解釈ができますが、ビジネスでは「機能性や美しさ」をどのように捉え、それをどう形にするかを考えるプロセスを指すこととして用いられることがあります。これは事業を行うことにおいて、デザインが最も本質的に関与する領域です。
この考慮する過程は、ただ単に機能性を追加したり装飾したりと「上乗せ」で仕上げることではありません。場合によっては、シンプルな魅力を活かす選択をすることもあります。つくる商品やサービス、ブランドの特性に応じて、適切なバランスや方向性を見極め、「どうあるべきか」を考えるプロセスなのです。
UIデザインの改善に興味がある方も、まずは「何が求められているのか」「何が最適なのか」を考えることが、最初の一歩となります。
デザインの本領発揮できる範囲を見極める
まず思い浮かぶのは、「そのデザインに触れる人々」との接点です。デザインは課題を解決する手段であり、ユーザーや関係者に対してその効果を発揮します。
さらに、デザインは単なるビジュアルだけでなく、「コミュニケーションツール」としての役割も果たします。例えば、オンラインWebデザインツール「Figma」は、ブラウザ上でワイヤーフレームを共同編集できる機能が評価され、2022年には100億ドルを超える評価額を記録しました。このようなツールは、多国籍や異なる文化背景を持つメンバーが集まるチームでも、共通認識を築くための重要な手段となっています。
言葉や会話だけでは伝えにくい内容を、デザインが補完し、チーム内外のコミュニケーションを円滑にする場面は今後さらに増えるでしょう。また、商品やプロダクトを通じて社会にメッセージを発信する際、「人々の関心を引く」ための手法としてもデザインは重要です。
デザインは、単に見た目を整えるものではなく、伝達や共感を生む力を持ったツールであり、ビジネスにおける欠かせない存在です。
まとめ
デザインは、商品やサービスの特性を深く理解し、最適なバランスや方向性を見極めることで、ビジネスの目標に直結する力を持ちます。「伝える力」を備えた表現方法であり、それは直接的だけでなく、ユーザーや関係者との接点で間接的にもその本領を発揮し、もっと大きな社会に向けて関心を引くメッセージを届ける手段としても重要です。言葉だけでは伝わりにくい情報を可視化し、コミュニケーションツールとして共感を生み、プロジェクトを前進させる役割も果たします。
しかし、こうしたデザインの力を十分に引き出し、目的達成に結びつけるには、単にデザインを施すだけではなく、適切に活用する手腕も必要です。
デザインは、見た目を整えるだけではなく、真の目的に対して誠実に向き合い、取り組むことで、初めてユーザーの満足度を高める力を発揮します。ビジネスにおいてデザインは切っても切り離せないものであり、目的達成のためには必須項目なのです。
3.UIデザイン改善の「小さな一歩」|取り組み施策ガイド7選
とはいえ、具体的な内容を知りたいと思う方は少なくないでしょう。
今回の【入門編】では、大きな予算をかけずに始められるUIデザイン改善の取り組みについて触れていきます。取り組みやすさと効果が出やすいの2軸で「★~★★★★★」で評価しましたので、参考になさってください。
CTA(Call to Action)ボタンの改善 (★★★★★)
具体的な改善方法: ボタンの色やサイズ、配置を目立つように変更。アクションを促す文言(例:登録する → 今すぐ登録する)を改善。
期待できる効果: コンバージョン率(CVR)の向上。
ファーストビューの最適化 (★★★★★)
具体的な改善方法: ページ上部に重要な情報を配置。ユーザーにメリットを直感的に伝えるメインビジュアルやキャッチコピーを見直す。
期待できる効果: 離脱率の低下、閲覧時間の向上。
フォーム入力フィールドの簡略化 (★★★★★)
具体的な改善方法: 入力必須項目を減らし、1ページ内で入力を完結させる。リアルタイムのエラーメッセージを導入。
期待できる効果: フォーム完了率の向上、ユーザー体験の改善。
レスポンシブデザインの確認と微調整 (★★★★☆)
具体的な改善方法: モバイルデバイスでの見え方や操作性を確認し、クリックしやすいボタンサイズやタッチ領域を調整。
期待できる効果: モバイルユーザーのエンゲージメント率の向上。
フォントの見直しとサイズ調整 (★★★☆☆)
具体的な改善方法: 読みやすいフォントを採用し、行間や文字間隔を適切に設定。重要な見出しはサイズを大きく。
期待できる効果: 情報伝達の向上、直帰率の低下。
ページ読み込み速度の改善 (★★★☆☆)
具体的な改善方法: 不要な画像やスクリプトを削除し、画像を圧縮。Google PageSpeed Insightsで速度を確認。
期待できる効果: ユーザー満足度の向上、SEO効果の向上。
ナビゲーションメニューの簡略化 (★★☆☆☆)
具体的な改善方法: メニュー項目を必要最低限に絞り、主要な行動を促すリンクを目立たせる。
期待できる効果: サイト内回遊率の向上、離脱率の低下。
画像とアイコンの再評価 (★★☆☆☆)
具体的な方法: 無駄のない適切な画像を使用し、アイコンを活用して直感的なナビゲーションを提供。
期待できる効果: 操作のしやすさ向上、直帰率の減少。
これらの取り組みは、最小限のリソースで始められるうえ、効果をデータで測定しやすい内容です。小さな改善を積み重ね、UIデザインの価値を確実に実感できるよう進めていくことをおすすめいたします。
4.専門的な部分はデザイナーやツールでカバー
前章でお伝えした「具体的なUIデザイン改善方法と期待できる効果」ですが、一歩踏み出しやすい項目をピックアップし掲載はしましたが、とはいえ、デザインの知識や経験がないまま改善に取り組んでも、十分な効果を得られない可能性があります。
そこで、専門的な部分はデザイナーに相談するか、デザインツールを活用することでカバーする方法を検討してみましょう。現在は無料やお試し版が利用できるツールも多く、コストを抑えてスタートすることが可能です。
また、改善効果を高めるには、必要な情報をピックアップし、社内で優先度や緊急度を見極めることが重要です。これにより、適切な計画を立ててデザイン改善に取り組む土台を整えられます。
例えば、「UIナビ」では無料で1ページ分プロのデザイナーによる診断を受けることができます。デザイン改善のための足掛かりとして無料で第三者のプロの力を借りてみられるサービスはきっと新たな気づきを生み出すでしょう。
まずは、小さな取り組みから始め、デザイン改善の価値を実感できる結果を目指して目標達成のために貢献する課題を発見しましょう。
この情報は役に立ちましたか?
カテゴリー: