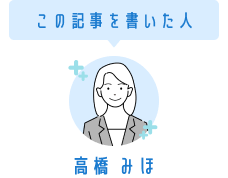![]()
外部デザイナーとの付き合い方、なんとなくで進めていませんか? 「発注のたびに説明が大変」「品質が安定しない」「小さな修正が頼みにくい」——そんな悩みが少しでもあるなら、契約の見直しが大きな打開策になるかもしれません。
本記事では、定額契約や長期パートナーシップの活用により、業務効率と成果を最大化するための契約の最適解を具体的に解説します。ただの外注から“信頼できるパートナー”へのステップアップを考えるタイミングです。
この記事の目次
1.外部デザイナー活用の変化
![]()
企業におけるデザイン業務の担い手は、かつて「社内の専任デザイナー」か「案件ごとのスポット発注」かのほぼ二択でした。しかし近年では、デザイン領域に求められるスピードと専門性の高まりを背景に、外部デザイナーの契約形態や活用法にも大きな変化が起きています。
- 単発依頼中心から、継続的パートナーシップへのシフト
- UI/UXやモーションなど、デザイン職の専門分化と役割の明確化
- リモートワーク・オンラインツールの普及による地域制約の撤廃
- 生成AIの台頭によるデザイン「設計」力の重要性の再評価
こうした変化を正しく捉え、自社に合った外部デザイナーとの付き合い方を再設計することは、制作物の品質や業務効率、ひいてはブランドの印象にまで影響する意思決定となりつつあります。
過去から現在への変化とそれを支える背景をひもときながら、今求められる契約の考え方や見直しのポイントを整理していきます。
2.外部デザイナー契約の変化と、その背景
短期契約から長期パートナーシップへ
かつては、LP制作やバナーなど単発で制作物を依頼するスタイルが主流でした。しかし、ブランド設計・運用の継続性が重視されるようになる中で、外部パートナーにも中長期的な関与が求められるケースが増加しています。
デザインの世界でも「文脈」を理解した上での提案が求められるため、「都度ゼロから説明するコスト」を避けるためにも継続的な関係が合理的なのです。
フリーランスから法人まで、多様な委託パターン
フリーランスデザイナーの専門性・柔軟性を活かした契約から、制作会社やデザイン特化企業との業務委託契約まで、委託形態はより多様になっています。自社の体制や制作量に応じて、稼働量と柔軟性のバランスを見極めたパートナー選びが重要になっています。
スキルの細分化が契約の複雑さを加速
一言で「デザイナー」といっても、求められる専門性は年々細分化しています。
- UI/UXデザイン
- Webデザイン・HTML設計
- モーションデザイン・アニメーション
- スライド整形・プレゼン設計
- イラストレーション・図解構成
- バナー設計・SNSデザイン など
そのため、「すべてを1人に求める」よりも、「必要な領域で適切な専門家とパートナーシップを結ぶ」ことが、効率的かつ質の高い成果につながると考えられています。
グローバル対応・リモート化の後押し
ツールやワークフローの整備が進んだ今、外部パートナーに求められるのは「居住地」ではなく「スキルとコミュニケーション能力」です。特にFigma、Slack、Notionなどのツールの浸透により、国内外を問わず「社内と同等のスピード・透明性」で連携することが可能になりました。
3.現在の契約内容を見直すためのチェックポイント
![]()
外部パートナーとの契約が当たり前になる今、次のようなポイントを確認し、今の契約が本当に最適かどうかを見直すことが重要です。
コストとクオリティのバランス
- 単価契約 vs 時間契約
単価契約は「何をいくらで発注するか」が明確な反面、変更や追加対応のたびに再調整が必要となり、柔軟性に欠けるケースが多いです。 一方、時間契約(例:月20時間稼働)や定額制であれば、小さな修正や複数案件をまたぐ対応にも柔軟に対応可能になります。
- 長期契約の方が実質コストが下がるケースも
都度発注や社内の説明コスト、資料作成時間を考えると、長期的な契約の方が総工数は削減され、結果としてコストパフォーマンスは高くなる傾向があります。
契約の柔軟性
- 固定工数契約
計画的な業務設計が可能となり、突発案件にも対応しやすくなります。
- プロジェクト単位契約
明確な範囲設定ができる反面、“あと少し”に対応しづらいという弱点もあります。
サブスクリプション型のように、「月内での調整やスライド・画像の追加制作にもすぐに応じてもらえる」契約形態は、実務担当者の柔軟性を大きく後押しします。
具体的なサービスとして定額でプロのデザイナーの工数を確保できるサービスもございますので、こちらもあわせてご参考下さい。
デザイン資産の管理と再利用
- 納品データの管理ルールは明確か
Illustrator・Figma・Canvaなど、制作ソフトごとの取り扱いに関する合意や、著作権・使用許諾の明文化は、後のトラブル回避に不可欠です。
- デザイン資産が再利用可能な形式か
- 過去の制作物を流用・改変可能かどうかは、新たなプロジェクトのスタートスピードに直結します。
4.契約の見直しで得られるメリット
ここでは、契約を「都度発注型」から「長期・定額型」に見直すことで得られる具体的なメリットを紹介します。
1. コスト効率の向上
- 都度の見積もり・発注・検収の手間を削減
- 社内の調整コスト(レビュー回数・指示出し)が削減
- 小さな業務を遠慮なく依頼でき、社内メンバーの手戻りが減少
2. デザイン品質の安定
- 継続契約により、デザイナーの企業理解が進む
- ブランドトーンやルールが守られるため、表現の一貫性が維持されやすい
3. チーム連携の効率化
- SlackやNotionを通じて社内メンバーとの連携がスムーズに
- 仕様整理や改善提案も、定期的にアウトプットされる文化が育つ
4. 担当者の「発注工数」そのものが削減される
- 毎回「どう頼めばいいか」を考える必要がなくなる
- 「イチからの資料作成」や「発注テンプレの更新」が不要になる
- 結果として、担当者の時間が“本質的な判断や戦略設計”に使えるようになる
5.今後のデザイナー活用戦略
社内デザイナーとのハイブリッド運用
たとえば以下のような組み合わせが効果的です。
- 社内デザイナー:戦略設計・上流のトーン整備を担う
- 外部パートナー:制作実務や定常業務(LP修正、バナー量産など)を担当
こうすることで、社内の限られたリソースを本質的な判断に集中させつつ、制作現場の手戻りや非効率を抑えられるハイブリッド体制が構築できます。
業務委託 vs サブスク型:どちらを選ぶべきか?
- 業務委託契約は「大規模リニューアル」や「ブランド刷新」など、一定期間に集中した取り組みに適しています。
- 一方、サブスクリプション契約は「月々発生する制作物対応」や「相談・修正のしやすさ」を優先したい場面で活躍します。
両者は競合関係ではなく、役割が異なる補完関係です。自社の発注量、制作スパン、社内体制に応じて、状況に応じた契約形態の選定がカギとなります。
専門性の高いデザイナーをどう見極めるか?
- UI/UXやモーショングラフィックスなど、技術領域の専門家には成果物だけでなく「思考プロセス」や「設計意図」まで確認できる関係構築が重要です。
- 「言われたものを作る」だけでなく、「課題の解像度を一緒に上げられる人材」を見極めましょう。
外部デザイナーにもインナーブランディング視点を
継続的に依頼するデザイナーには、企業のビジョン・価値観・商品理解など、“共にブランドを育てる”視点を持ってもらうことが成果の質に直結します。
そのためには、ブランドガイドラインの共有だけでなく、対話やフィードバック文化を含めた内製体制のような温度感の構築が鍵となります。
![]()
6.契約の見直しは、業務設計そのものを変える一手に
今回ご紹介してきたように、外部デザイナーとの契約形態は、単なる外注管理ではなく「業務の質と効率をどう設計するか」を左右する重要なテーマです。
特に以下のような課題を抱える企業・担当者の方は、契約見直しをきっかけに、業務の流れそのものを再設計できる可能性があります。
- 都度発注が煩雑で、担当者の業務が圧迫されている
- デザイナーの入れ替わりにより表現のブレが生じている
- 軽微な依頼や相談がしにくく、非効率を感じている
- 社内にノウハウが蓄積されないまま、納品物だけが増えている
定額制でデザイナーをパートナーにしませんか?
一定の稼働時間を月額で確保できるデザイナーサブスクリプション型サービスをご提供しています。
- 月20時間から利用可能
- 対応内容の範囲指定なし
- LP・バナー・SNS画像・スライド・UIパーツなど幅広く対応
- 修正回数の制限なし
「柔軟性をもったデザイナーが欲しい」「増え続けるデザイン業務に社内だけで対応しきれない」といった状況に応じ、外部にいながら内製のように機能する新たな選択肢としてご活用いただけます。
もし、
- 自社に合った契約形態を一度見直してみたい
- 今の外注先との関係で課題を感じている
- サブスク型の活用メリットを具体的に検討したい
という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。 実績資料や活用例のご案内、無料相談も随時受け付けております。
デザイン業務のあり方を見直すことは、チームの働き方そのものを変える第一歩です。 最適な体制づくりをご一緒できれば幸いです。
7.FAQ
Q. 外部デザイナーとの契約形態にはどのような種類がありますか?
A. 単発依頼、プロジェクト単位、時間契約(時給・日給)、月額制(サブスクリプション型)などがあり、業務内容や継続性によって最適な形式を選ぶことが重要です。
Q. デザイナーとのサブスク契約にはどんなメリットがありますか?
A. 柔軟な対応、コスト予測のしやすさ、継続的な品質維持、軽微な修正依頼のしやすさなど、日常的に発生するデザイン業務に対して高い親和性があります。
Q. 外部デザイナーに依頼する際、気をつけるべきポイントは何ですか?
A. 著作権の帰属、コミュニケーションツールの整備、ブランドトーンの共有、対応スピード、過去実績の確認などを事前に明確にしておくことが肝要です。
この情報は役に立ちましたか?
カテゴリー: