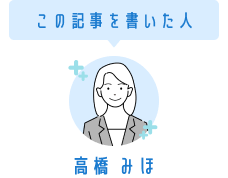デザイナーとの認識ズレを解消!非デザイナーが押さえておくべきユーザビリティの基本
![]()
「リニューアルしたのに、成果が上がらない」 「頼んだ通りにできているはずなのに、使いづらい気がする」 「打ち合わせでは伝えたつもりなのに、どうしてこうなるんだろう」マーケティング、広報、営業企画──多くの非デザイナーが、日々の業務の中でデザイナーと関わるなかで、このような“認識のズレ”に直面しているのではないでしょうか。
本記事では、特別なデザイン知識がなくても理解できる「ユーザビリティ(使いやすさ)」の考え方と、その実践的なヒントをご紹介します。
この記事の目次
1. なぜ“ユーザビリティ”が重要なのか
見た目がきれい=成果が出るとは限らない
「デザインが洗練されている」「トレンド感がある」──これらは確かに大切な要素です。しかし、本当にユーザーが求めているのは“目的を迷わず達成できること”です。
たとえば、採用サイトをおしゃれに刷新したのに応募数が減ったとしたら、どこかで「探しづらい」「気づけない」状態が発生している可能性があります。これはまさに、ユーザビリティの問題です。
UI/UX/ユーザビリティの違いを整理する
- UI(ユーザーインターフェース) 画面の見た目、操作部分のこと
(例:ボタン、フォーム、レイアウト) - UX(ユーザー体験) 使っていて「快適」「わかりやすい」と感じる体験全体
- ユーザビリティ UXの中でも、「迷わず、スムーズに使えるか」を示す機能的な使いやすさ
つまり、ユーザビリティとは「UIの先」にある“ユーザー行動のしやすさ”に直結する要素なのです。
認識ズレが起きる理由とは?
制作の現場では、「かっこいい」「雰囲気がある」などの主観が先行し、ユーザーの動きや感情が後回しになることがあります。一方、発注側が「見栄え」と「成果」を混同したまま依頼を進めてしまうと、「こんなはずではなかった」というズレが生まれます。
特にリニューアル後にCV(コンバージョン)が低下したケースでは、ユーザビリティの低下が見逃されていることが多いのです。
2. 非デザイナーが最初に押さえるべき基本原則
Nielsenのユーザビリティ10原則
デンマークの人間工学研究者ヤコブ・ニールセンは、優れたユーザビリティの指針を10項目に整理しています。以下は、そのエッセンスです。
- 今どこにいるか、何が起きているか分かる
- ユーザーの言葉で書かれている
- 間違えても戻れる/やり直せる
- 操作がいつも同じなので迷わない
- 間違いを起こさせない設計になっている
- 一度覚えたことを再び学び直さずに済む
- 初心者にも上級者にも快適に使える
- 画面がごちゃついておらず、見やすい
- エラーが出たときに、原因と対処法がわかる
- 困ったとき、助けがすぐ見つかる
直感的に見るなら:「パッと見」「動き」「スムーズさ」
難しく考えなくても、実務では次の3点に着目すれば十分です。
- パッと見:最初に見たとき、何のページか一目で分かるか
- 動き:押したら反応があるか、変化が自然か
- スムーズさ:戻る・探す・行動するのが手間なくできるか
アクセシビリティとの違い
ユーザビリティが「全ユーザー向けの使いやすさ」なら、アクセシビリティは「高齢者や障害のある方など、多様なユーザーへの配慮」です。設計思想は共通しており、どちらも“誰でも迷わず使える”がゴールです。
「この画面は誰のものか?」を問い直す
画面の主語を「社内」から「ユーザー」へ切り替えましょう。
たとえば求人LPなら、「採用担当者の言いたいこと」ではなく、「応募者が知りたいこと」の順番で見せる必要があります。企画段階で“何に悩んでここに来るのか”を想像するクセをつけると、ユーザビリティ設計の精度が大きく変わります。
3. ユーザビリティの「悪例」に学ぶ設計ミス
情報過多による「伝わらない」状態
あれもこれも伝えたい気持ちは分かりますが、1画面に情報が詰まりすぎると、かえって何も伝わらなくなることがあります。
例:会社紹介が長すぎて応募ボタンが見えなくなっている求人LP
※UIUXを考慮したデザインからIndeedなどへの各種連携、運用、保守まで多岐にわたった求人サイト、求人メディア制作サポートを提供しております!ご興味がある方はこちらからお問い合わせください。
誘導ミスによる「迷子」
- 「資料請求はこちら」と「問い合わせはこちら」が並んでおり、どちらから進めばいいか分からない
- メニュー項目が多すぎて、興味のある情報にたどり着けない
こうしたケースでは、本当にしてほしい行動にユーザーを導けていないことが問題です。
CTA(行動ボタン)の埋没
- ボタンが目立たない
- 似たような色ばかりでクリックされにくい
- ページ下にしかCTAがない
CTAは行動の「出口」です。見逃される位置やデザインだと、いくら内容が良くても離脱されてしまいます。
非デザイナーに多いレビュー時の見落とし
- リンクだと気づかない文字(下線やホバーがない)
- モバイルでの改行崩れやテキスト詰まり
- エラー表示が出ず、入力後にリセットされるフォーム
非デザイナーが特に意識したいのは、「デザイン“された”ように見えても、実際には使えない部分が潜んでいる」ことです。
フィードバックが曖昧だとズレが広がる
NG例:
- 「もう少しかっこよくしてください」
- 「直感的にお願いします」
- 「ユーザー視点でお願い」
これらの言葉は曖昧で、“誰に対して、どうしてほしいか”の説明が抜けているため、認識のズレが広がります。
![]()
4. 成果につながるユーザビリティ設計の視点
ユーザーフローを描く:行動の地図をつくる
たとえば…
- 検索エンジンからTOP
- 「仕事内容へ」→「社員インタビューへ」
- 応募要項→エントリーフォーム
このように、想定されるルートを可視化することで、迷わず進める情報導線を設計できるようになります。施策前に一度、紙でもスプレッドシートでも構わないので、ユーザー目線で“移動の地図”を描いてみることをおすすめします。
コンテンツ設計における「入口」と「出口」の明示
サイトやページには、常に目的別の入口と明確な出口(行動の着地点)が必要です。
- 入口=ユーザーの関心・悩みに共感する見出しや導入文
- 出口=「資料請求へ」「求人一覧へ進む」などの行動導線
これが曖昧なままだと、ユーザーが「今、どこにいて、どこへ進めばよいか」分からずに迷子になります。
テキスト・画像・CTAの役割整理
- テキスト:理解を促す。情報や理論を「言葉」で伝える。
- 画像/動画:印象づけ・共感を生む。空気感や人物像などを補完する。
- CTA(Call To Action):次の一歩を示す。迷わず行動してもらうための「出口」。
この3つの役割が混在したままコンテンツが作られると、ユーザーの視線はあちこちに分散し、訴求力が弱まります。
ファーストビューの“期待づけ”で離脱を防ぐ
ユーザーがサイトに来て最初に見る画面(ファーストビュー)は、3秒以内に「ここには欲しい情報がある」と思ってもらえるかが鍵です。
そのためには…
- キャッチコピーやメッセージが明確
- デザインで視線誘導ができている
- CTAが分かりやすく設置されている
- 無駄な装飾や情報過多がない
見た目の印象よりも、「自分の目的に合っていそうか」の直感を後押しできる設計が重要です。
5. メディアや求人サイトにおける具体的な活用場面
ここでは、実際の運用現場に即した活用シーンを想定して、ユーザビリティの考え方を具体的に落とし込んでいきます。
![]()
求人サイト:応募率を左右するUI設計
- CTAボタンの配置場所と色
- 求人情報の要点をファーストビューに配置
- 採用の流れや勤務条件は、見出し付きでまとめる
- 応募後の流れや問い合わせ先も明記する
読み手が「ここなら応募しても安心」と思えるよう、“選ばれる企業”としての誠実なUI設計が効果的です。
メディアサイト:記事導線と回遊性を高める
- タグやカテゴリの自動リンク
- 「おすすめ記事」や「人気記事」の掲載場所
- 記事下CTAの設置(ホワイトペーパーDL・資料請求・フォーム導線など)
- モバイル表示時のスクロール軽減と可読性の維持
読者にストレスなく記事を読み進めてもらい、「気づけば離脱せず複数記事を読んでいた」という状態を作り出すための“導線設計”が鍵です。
スマホユーザーへの配慮:必須のユーザビリティ対策
スマートフォンからのアクセスが過半数を占める現在、以下のポイントは必須です。
- タップできる範囲を広めに設計
- フォントサイズは14px以上を目安に
- ハンバーガーメニューでも優先導線は見える位置に出す
- 縦長スクロール前提で“1スクリーン=1情報”に抑える
実務に使えるチェックリスト例
- □ 最初に何をするサイトかが明確
- □ CTAボタンの位置と文言が適切
- □ 説明が簡潔で、情報が過不足ない
- □ 動作やホバーが直感的である
- □ モバイル対応が適切にできている
- □ 離脱されやすいページに手当てがされている
こうした項目を、制作中や運用中に“言語化された視点”として使えると、プロジェクト全体の再現性が高まります。
6.デザイナーと協業するための“伝え方”の工夫
プロジェクトの進行では、実はここが最重要ともいえる章かもしれません。
「感覚」ではなく「目的」から会話する
NG:「もっと柔らかい印象にしてほしい」 OK:「初めて求人を見る学生でも安心して読み進められるようにしたい」
NG:「かっこよく」 OK:「30代の管理職経験者が“スマートな職場”だと感じるデザインを意識したい」
このように、“どんな人が、どう感じて、どんな行動をしてほしいか”を共有することが成果につながります。
避けたい抽象表現
- 「なんとなく違う」
- 「直感的じゃない」
- 「もっと情報を整理して」
こういった指摘は、制作者からすると「結局どう直せばいいの?」と手が止まる原因になります。
ワイヤーフレームや構成図を活用する
非デザイナーがビジュアルで説明できなくても、「この順で読ませたい」「このパートの後にアクションを取りたい」という意図が図解やラフでも伝えられると、認識のズレが少なくなります。
フィードバック例文
- ✕「いい感じに仕上げてください」
- ○「応募ボタンは画面に入ってすぐ目に入るようにしたいです」
- ✕「もうちょっと派手に」
- ○「飲食・小売向けなので、賑やかさや活気のある印象を出したいです」
言葉の置き換え力は、非デザイナーにとって最大のスキルといえるかもしれません。
7. 限られた予算・期間で成果を出すために
![]()
最後に、実務上避けては通れない“現実的な制約下”でユーザビリティを活かす方法をまとめます。
企画段階からユーザビリティ視点を入れるメリット
- 途中の手戻りを防げる
- 課題発見が早くなる
- 定量目標に結びつけやすくなる(CV率・直帰率など)
「デザインが固まってから考える」のでは遅すぎることもあります。
定量指標で見る成果のヒント
- CV率の変化:導線やCTA文言を変えたあとに注視
- 直帰率:情報設計やファーストビューの改善指標に
- 平均滞在時間:記事やコンテンツの引き込み力の指標
定性検証:ユーザーテストやヒューリスティック評価
- 実際のユーザーに触ってもらい、「わかりにくい」「押しづらい」と感じる場面を観察する
- 専門家による簡易評価(5分で気づける粗を拾う)
どんなときに相談したほうがいい?
- 社内制作では改善案に行き詰まっている
- ターゲット向けの動線設計に自信がない
- デザインは美しいが、数字が伸びない
- 短期間でも成果に寄与する提案が欲しい
制作会社に相談することは、丸投げではなく「戦略を共につくるパートナーを得ること」です。
求人サイト、求人メディア制作について、なんでもご相談ください!
附録|FAQ
Q1. ユーザビリティとアクセシビリティの違いとは何ですか?
- ユーザビリティは「すべてのユーザーにとっての使いやすさ」を指し、情報の見やすさや操作のしやすさが対象です。一方、アクセシビリティは「特定の条件を持つユーザー(高齢者・障害者など)への配慮」を意味し、色覚設計や読み上げ対応などが含まれます。
Q2. サイト改善でユーザビリティをチェックする際、どこから始めればよいですか?
- まずはユーザーフローを整理し、「訪問者が何を目的に訪れ、どの情報を探しているか」を可視化しましょう。そのうえで、CTAの配置・読みやすさ・スマホ最適化など、重要な接点から優先的に確認するのが効果的です。
Q3. デザイナーへの依頼時、ユーザビリティ観点で意識すべきことは?
- 感覚的な表現(例:「なんとなく見づらい」)ではなく、「誰が・どのタイミングで・どの行動をとってほしいか」といった目的と利用シーンを具体的に共有することが、認識のズレを防ぎ、ユーザビリティ向上につながります。
この情報は役に立ちましたか?
カテゴリー: