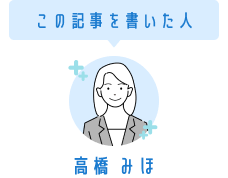よく耳にするけれど知らないシリーズ|脆弱性(ぜいじゃくせい)
インターネットは今や、私たちの生活や仕事に欠かせない存在です。しかし、その便利さの裏には、思わぬ危険が潜んでいることをご存じでしょうか? それが 「脆弱性」 です。
ニュースやパソコンの警告メッセージで目にすることがあるかもしれませんが、「脆弱性」という言葉の意味を正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。もし、企業で働く誰もがこのリスクを理解し、適切に対策できるようになれば、サイバー攻撃の被害を大幅に防ぐことができます。
この記事では、 「脆弱性とは何か?」 という基本的な内容から、それが企業にどんなリスクをもたらすのか、そして具体的な対策方法 まで、わかりやすく解説します。難しい専門用語はできるだけ避けて説明していきますので、「ITは苦手…」という方も、安心して読み進めてみてください!
この記事の目次
1.脆弱性とは何か
脆弱性とは、ソフトウェアやシステムに存在する欠陥や弱点のことを指します。実は医療の現場でも使われる言葉で、その意味はもろくて弱い性質または性格などを指し、どちらも共通して弱く・傷つけられやすい様子を表しています。
システム内に存在する欠陥が外部からの攻撃によって悪用されると、情報漏洩やシステムの不正操作といった被害が発生する可能性があります。ではなぜ、脆弱性は起こるのでしょうか。原因はいろいろと考えられますが、多くの場合プログラムの設計ミスや開発中の見落としなどに起因します。特に、インターネットに接続されたデバイスでは、脆弱性が存在することで外部からの不正アクセスが可能となるため、非常に危険な状況に発展する恐れがあります。
2.具体的な「脆弱性」を理解する
発生する原因
脆弱性は主にプログラムの設計ミスや、開発中に気づかれなかったバグが原因で発生することが多いです。また、新しい技術や通信規格を導入する際に、適切な検証が行われなかった場合にも脆弱性が生じることがあります。たとえば、未熟なプログラマーがセキュリティ面を軽視してコーディングを行った結果、意図しない形で外部からの入力を受け入れてしまうケースなどが挙げられます。
その他にも不要な権限を与えてしまい、外部からアクセス可能になっている権限設定の誤りや、古いソフトウェアのセキュリティに未更新の箇所があり、その箇所が脆弱性となるなど、様々なパターンがあり得ます。
PCのアラートなどで目にする「脅威」との違い
「脅威」とは、脆弱性を利用して実際に攻撃が行われる可能性を指す言葉です。
脆弱性が存在しても、それがすぐに脅威に直結するとは限りませんが、脆弱性が放置されれば攻撃者にとっては格好の的となり、脅威が現実のものとなる可能性が高まっていきます。PCのアラートで表示される脅威情報は、こうしたリスクをユーザーに警告するものであり、自分たちを守る行動を促す重要なサインなのです。
3.脆弱性における危険性
マルウェアへの感染リスク
脆弱性を放置すると、マルウェアに感染するリスクが高まってしまいます。マルウェアは、システムに不正な動作を引き起こす悪意のあるソフトウェアやコードの総称のことです。脆弱性を利用してシステムに入り込むことで、データの破壊や情報の盗難、さらにはシステムの乗っ取りを行うことができるので、非常に危険です。
悪意あるプログラムの侵入リスク
脆弱性が存在することで、本来セキュリティが機能しているところに抜け穴ができ、そこから悪意あるプログラムがシステムに侵入しやすくなるようなイメージをもっていただけるとわかりやすいでしょう。例えば、フィッシングメールや不正なファイルを通じてシステムに侵入し、機密情報を盗んだり、システム全体を操作不能にすることが可能となるのです。これにより、企業や個人の信用が大きく損なわれる危険性に繋がる恐れがあります。
4.脆弱性が原因で発生した有名事例
◆2017年「Equifax社」個人情報流出事件
米国の信用情報機関Equifax(エクイファックス)は、Apache StrutsというWebアプリケーションフレームワークの脆弱性(CVE-2017-5638)が原因でハッキングを受け、約1億4,700万人分の個人情報(名前、社会保障番号、運転免許証番号、クレジットカード情報など)が流出しました。
アメリカ国内のみならず、カナダやイギリスの顧客情報も流出し、同社は約7億ドル(約7,700億円)の和解金を支払うこととなりました。適切なパッチ適用が遅れたことが主な原因とされ、セキュリティ管理の甘さが指摘されました。
◆2021年「Log4j(Log4Shell)」脆弱性による大規模被害
Javaのロギングライブラリ「Log4j」に重大な脆弱性(CVE-2021-44228、 通称「Log4Shell」)が発見され、悪意あるコードを簡単にリモート実行できる状態になりました。多くの企業や政府機関が使用するシステムに影響を与えました。
Amazon、Apple、Google、Microsoftなどの大手企業のシステムも影響を受け、多くのサイバー攻撃の標的となりました。問題が発覚した直後から各企業が対応に追われ、プログラムの追加修正の適用が急務となりました。
◆2014年「ベネッセ」個人情報流出事件
教育企業ベネッセのシステムにおいて、セキュリティの甘さを突かれ、約3,500万件以上の顧客情報(氏名、住所、電話番号、生年月日など)が外部に持ち出されました。内部関係者による情報の不正持ち出しが原因でしたが、システムのアクセス制御の脆弱性が悪用された形です。
ベネッセは顧客対応のために200億円以上の費用を負担し、企業の信用が大きく失墜しました。システムのアクセス管理の重要性が改めて認識されるきっかけとなりました。
◆2020年「三菱電機」のサイバー攻撃事件
三菱電機は、外部からのサイバー攻撃によって大量の社内情報が流出したと発表しました。この攻撃は、中国のハッカーグループ「Tick」が関与しているとされ、VPN機器の脆弱性を悪用して不正アクセスが行われた可能性が高いとされています。
企業秘密や防衛関連情報の漏えいが懸念されました。三菱電機は、セキュリティ体制の強化とともに、外部のサイバー攻撃に対する防御策の見直しを進めることとなりました。
その他にも、個人情報の大量流出や、企業のサーバーが攻撃されて大規模なサービス停止が発生した事例もある。これらの事例は、脆弱性がいかに重大な結果を招くかを示しています。
5.脆弱性に対する企業の予防と対策
多くの企業は、脆弱性によるリスクを最小限に抑えるため、様々な対策を講じています。まず、ソフトウェアのアップデートを定期的に行い、最新のセキュリティパッチを適用することが基本です。また、社内のITシステムに対しては定期的なセキュリティ診断を実施し、潜在的な脆弱性を早期に発見できるよう、運用フローが定められています。さらに、大切なこととして、従業員のセキュリティリテラシーを高めるための教育や訓練も欠かせないポイントになります。
6.まとめ
脆弱性は、情報化社会において避けては通れないものです。しかし、適切な対応を行うことで、そのリスクを大幅に軽減することがは十分可能です。個人や企業が安全にITを活用するためには、脆弱性の存在を正しく理解し、必要以上に恐れず、常に最新の情報をもとに対策を講じることが求められます。今後も、私たちはこの脆弱性を取り巻く問題に対して意識を高め、安全性を享受するための努力を続けていく必要があります。
脆弱性という単語を正しく理解し、過度に怯えることなく毅然とした態度で企業のセキュリティ環境を守っていきましょう。
この情報は役に立ちましたか?
カテゴリー: